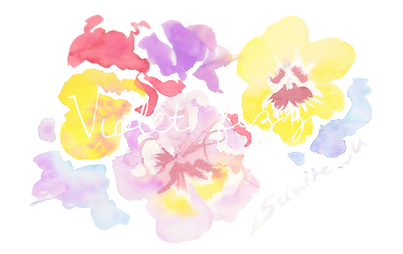大切に瓶詰めされていたのは、植物の種だった。
色も形も様々に、小さな種がみっちりと詰められた小瓶は、実家の食器棚の上の方に大切にしまってあった。引っ越しのたびに自宅の庭から種を収集して、母から父へと受け継がれて、ついに私の自宅へやってきた。
時間を止めた種たちは、眠っているのか、死んでいるのかわからないけれど、きっとどれかは目覚めてくれるだろうと、いくつかの植木鉢にそっとタイムカプセルを仕込んでみた。
一週間たったある日、にょきっとした緑の芽を見つけた。
その種は、父が恩師から譲り受けたという台湾の朝顔。
いつぞや玄関に咲いていた、その艶やかな紫色を見て、父は嬉しそうにしていた。
まるで自身の役目を思い出したかのように、目覚めた種。
芽の先っぽには、まだ黒い種の帽子をかぶっていて、まるでむずがるように伸びをしている。
数日たって、すぐ隣に、またもうひとつの芽が出てきた。
「その種は…心のポケットにひとつ…」というような詩が添えられた、父の絵を思い出した。
この花が思い切り咲ける場所を想像しながら、朝晩の水遣りを日課する毎日。
目覚めの時を、植物たちはよく心得ているのだ。